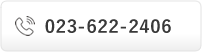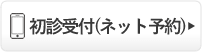ブログ
2025.04.09
春の花-梅
4月に入り、今日はあちこちの小学校で入学式が開かれたようです。
新しいランドセルを背負って元気よく歩く姿が見かけられました。
入学式、というと桜のイメージですが、まだ桜は咲いていませんね。
桜ももう少しで咲きそうですが、その前に梅の花があちこちで咲き誇っています。
医院の梅はまだ咲きませんが、自宅の梅はとうとう満開になりました。
昨年は3月末の桜の日に満開になっていましたので、今年は少し遅れての開花です。
それだけ今年は気温が低い日が多いのだということを実感させられます。
実際、日中の日差しは暖かいですがまだまだ明け方は寒いですしね。
寒暖差に体調を崩す人もまだいらっしゃるのではないでしょうか。
これからはどんどん暖かくなっていってほしいものです。

2025.03.12
春の草花-フクジュソウ
最強寒波がようやく過ぎ去り、温かい日が多くなってきました。
風も次第に暖かくなり春の訪れを感じます。
春休みも近づき、旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。
気持ちもウキウキしてきますが、新幹線の連結部が外れるという思いもよらない事故がおこってしまい、
福島で乗り換えないと東京方面に行けないという、不便な状況になったのは困りものです。
早く解決されると良いのですが・・・
一方で花粉も舞い始め、私も含め花粉症の方にとってはつらい季節ですね。
地面にあった雪もほぼなくなり、様々な植物や生き物が活発に動き出したということではあるのですが・・・
当院の庭でも福寿草が咲きました。
毎年一番に花を咲かせてくれます。
福寿草を見かけると春が来たと感じます。
キンポウゲ科の植物で別名「元日草」といいます。
黄色の花はに日中は開いていますが、曇天や夜間は閉じています。
日中に開いているときは中央に光を集め保温力を高め受粉に利用するようです。
そして春が終わると地上に出ている部分は枯れて地中で休眠し翌春に備えます。
花粉はこまりますが、これから様々な花が咲いていくのは楽しみですね。

2025.02.21
雪の日
先週、今週と全国的に大寒波が来たために大雪が降っています。
山形市も先週日曜などは一日中雪が降っていました。すごい勢いで積もっていくので毎日必要で朝早くから雪をかいていました。
雪を置く場所も本当になくなりそうな久しぶりの大雪で、新幹線も止まるなど大きな影響が出てましたね。
今週も寒波が来ると言うことで、雪かきの日々が続くのかとげんなりしていましたが・・・
蓋を開けてみると今週は気温こそ低いのですが、雪の量は少なく、日中は青空が見えています。
雪も積もるどころか溶けていって大分少なくなりました。
青空を見上げると白鳥の編隊が飛んでいました。
冬に外国から山形に渡ってきてくれたのでしょう。
青い空に白い姿が映えますね。溶け込んでいくように消えてゆきました。
こんなに雪が少ないのはうれしい限りですが、ニュースで米沢などのすごい積雪を見ていると少し申し訳ない気持ちにもなりますね。


2025.02.03
節分
昨日、2月2日は節分でした。
あれ?節分は2月3日ではないの?と思いませんでしたか?
昨年の節分は2月3日、その前の年も2月3日でした。
なぜ今年は2日だったのでしょうか。
実は節分は固定された日ではないのです。
節分は立春の前日で、立春は地球の公転周期を元に決められます。
地球が太陽の周りを一周する公転周期は約365.2424日です。
通常閏年で調節していますが、二十四節季で考えていますので次第にずれていき、今年は立春が2月3日になりました。
このため節分も一日早い2日になったのです。
ややこしいですね。
さておき、今年もでんろくのお面をかぶって豆まきをしました。
なぜか今年はかわいい感じのお面でしたね。
今年の初夢は縁起が悪かったので、ここで邪気を追い払いたいものです。
「鬼はー外!福はー内!」

2025.01.12
初市
遅ればせながら、1月10日は初市が行われました。
今年は大寒波が押し寄せていたために雪が激しく降っていました。
このため昨年よりも人通りは少なかったかも知れません。。
初市は市神様をお祀りする行事でもあります。
市神様はもともと今の十日町のやまぎんカードサービスの前あたりにおかれていました。
高さ80cm、周囲150cmの安山岩の自然石で650年前に要石としておかれたものが、次第に人々にあがめられるようになったようです。
明治9年に文翔館に県庁が移転する際に湯殿山神社が建立され、そこに祀られるようになりました。
湯殿山神社に移った跡には石碑が建てられており、今も十日町を見守ってくれています。
縁起物として、カブやシラヒゲを供えられます。
今年は食べ物の屋台がほとんどで縁起物を売っている店は少ないように思いました。
当院の前にはキッチンカーがあつまり、カレーや明石焼き、あまり聞かないところではキューバサンド、フィッシュアンドチップスなど売っていました。
明石焼きはぐっど(以前の山形物産館)でも見かけることがありますね。
個人的には、サバイさんのタイラーメンが麺がもちもちしていておいしかったですね。
植木市の時にも来てくれていましたが、調味料かけ放題なのがさらに良い感じです。
紅の蔵からは獅子舞が出てきて、お客さんの頭をかんでいました。
獅子舞にかまれると、邪気が払われ、無病息災、学力向上になるようですので、皆さん今年一年健康に過ごせると良いですね。
私もかまれてみましたがどうなるでしょうか。


2025.01.01
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。2025年になりました。
朝起きたら雪が積もっており、雪かきから1年が始まりました。
雪かきしたら寝てしまったので初日の出を見るには至りませんでした。
雪をかいている頃は一部空が見えていましたが、今年は初日の出を山形で見ることはできたのでしょうか。
この年始には寒波が来るようなので、あまり雪が積もらないことを祈ります。
このブログ、1月1日の夜に書いていますが、今年は大きな災害が起きず1日が終わりました。
今年は平穏な年になってほしいですね。
今年も皆様のお役に立てるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
また、2025年のカレンダーに休診日を入れていないことに今気づきました。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。

2024.12.29
仕事納め
昨日、12月28日は仕事納めとなりました。
今年もいろいろなことがありましたが、皆さんに支えられ、メンバーが欠けることなく無事この日を迎えることができました。
振り返ると、今年は1月1日の能登の地震、翌日の飛行機事故から始まり、どうなるのかと不安がよぎる始まりでした。
その後も夏の猛暑、台風による川の氾濫と、年々自然の猛威が激しくなっていました。
今までは夏の暑さも問題なかった方も、今年の夏は体調を崩されたりしておられ、今年の夏は特別な印象でした。
暑さが11月まで続き、12月に入ると突然寒くなりました。
年々秋らしい期間が短くなってきています。
冬場に入るとコロナとインフルエンザが流行してきました。
特にインフルエンザは、今週に入ってから急速に増え、例年よりも激しい印象です。
年末年始、移動される方は気をつけてお過ごしください。
医院的には、HbA1cやCRPといった項目がその日のうちに測定できるようになったのは大きな変化でした。
今までは翌日まで待たなければいけなかったのですが、すぐわかるようになり治療方針も立てやすくなったのは助かっています。
気温が低いと暖まるまで使えないが欠点ですが・・・
来年もいろいろなことがあると思いますが、できれば良いことが多いと良いですね。
来年もよろしくお願いいたします。

2024.12.24
クリスマス
今日はクリスマスイブでした。
皆さんはどのようなクリスマスを過ごされたでしょうか。
私は自宅でまったりとしていました。
今年のクリスマスは、今季最初の最強寒波が訪れたため、外は真っ白の状況です。
気温も低く外を歩きまわるのはかなりつらい感じです。
昨日は今年初めての雪かきをしましたが、寒波自体はまだ続くようで、本番はこれからなのかも知れません。
ホワイトクリスマスになるのはうれしいのですが、降りすぎるのも考え物です。
そういえば、今年はカメムシが大量発生したために雪が多いのではないかと噂されていましたが・・・
実はこれ、科学的根拠はないようです。
雪が多いとカメムシが暖かい家の中に入り込んでくることが多いので、そう言われているのではないかとのことです。
また、雪と虫と言えばカマキリの卵が有名ですね。
卵が高いところにある年は雪が多い、というものです。
こちらは科学的根拠はあるようですが、いかんせんカマキリの卵をあまり見なくなりましたので、これで予測することも難しいですね。
今年の庭の草むしりで卵がついていた草を抜いてしまったのは、未だに後悔しています・・・
さあ、今年の雪はどうなるのでしょうか。



2024.12.08
山形市内の初雪
この週末はかなり冷えこみ、ついに市内にも雪が降りましたね。
土曜の朝起きたら、窓の外が白くなっていて驚きました。
幸いすぐ溶けましたが、今日になっても雪は降っていました。
晴れ間があったりして道路に積もりはしませんでしたが、千歳山は頂上からどんどん白くなっており、夕方には半分以上雪に埋もれていました。
これから本格的な冬シーズンがはじまります。
寒くなると、空気も乾燥し風邪もひきやすくなってきます。
風邪も咳が長引いたりすることが多く、なかなか大変な思いをします。
インフルエンザ、コロナ感染の方も徐々に増えてきている印象です。
うがい、手洗いといった感染予防の基本をしっかり見直しましょう。
また、寒くなると頭痛、めまい、便秘といった症状も起きやすくなってきます。
しっかり寝て、たべてと規則正しい生活を送ることで完全ではありませんが、予防できます。
寒いからといつまでも布団に閉じこもっておらずにリズムを崩さず生活していきましょう。
2024.12.01
秋の草花-ノコンギク
今年もついに最後の月になりました。
今年はお正月から様々なことがありましたが、それからもう1年がたってしまったとは信じられません。
北海道では雪も降ってきたようで、山形でも近いうちに雪が降るのでしょうね。
さて今回は、毎年当院で最後に咲く花の紹介です。
「ノコンギク」です。
キク科の花で、8-11月くらいに咲きます。
漢字では「野紺菊」と書きます。名前の様に紺というか濃い紫色の花を咲かせています。
写真を撮ると白っぽく見えるのですが、本当は非常に濃い色です。
今年も例年と比べ数が少ない様で、気温と関係があるのかもしれません。
地下茎があるので群落を作りやすく、まとまって咲いていることが多いです。
様々な色があるようですが、当院のものは鮮やかな紫色で、小さな可愛い花が風に揺れているのが目に入ります。
花言葉には「長寿と幸福」とあり、派手ではないですがみてると小さな幸福を感じられる感じがします。
かわいい花なのですが、この花がさくと今年も終わりという感じがしてさみしくもあります。