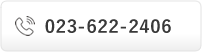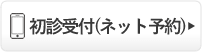ブログ
2021.10.11
秋の草花-ヤブラン
10月に入り早10日が過ぎてしまいました。
暗くなると庭からスズムシの鳴き声が聞こえてきます。
今回は紫色の花を咲かせていますヤブランです。
名前からはいかにもランの様ですが、キジカクシ科ヤブラン属の植物で、ランの仲間ではありません。
葉の形がランに似ているのでこの名前になったようですがユリの仲間に当たります。。
葉の間から花茎がでて、ここに紫色の花を多数咲かせます。
その後黒紫色の種子をつけます。
根は薬として扱われます。医療現場でもよく使われる麦門湯(バクモントウ)の材料になります。
薬局でも売っているのでご存じの方も多いと思いますが、風邪の引き始めによく使われていますね。
これからの季節、風邪を引きやすくなりますのでお気をつけください。
ところで、このヤブラン、学問草とも言われるようなのですが、調べてもなぜそう言われるのかわかりませんでした。
どなたか知っておられる方がいたら教えてください。
2021.09.26
秋の草花-ヒガンバナ
あっという間に9月も終わりに近づいています。
お彼岸も終わってしまいましたね。
今年はいろいろなことがあり残念ながらお墓参りに行けませんでした。
折を見て行ってきたいと思います。
さて、お彼岸といえばヒガンバナです。今年も庭の西側に咲いてくれました。
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の植物で、ほかに「曼珠沙華」や「リコリス」などとも呼ばれます。
昔から日本人に親しまれており、俳句などにもよく見かけます。
花と葉が別々に見られることで有名で、葉がないことで花の赤さがより際立っている感じがあります。
鮮やかな赤い花で群生しているのをみると、まるで本当に彼岸に渡ってしまっているかのような気持ちになります。
また毒草としても有名で鱗茎にはリコリンを主成分とするアルカロイドが含まれています。
花がないとニラなどと見分けがつきにくくなり、間違ってしまうことがあるようです。
球根のあるないで見分けはつきますが、すべて抜くわけにもいかないのが難しいところですね。
うっかり食べると本当に彼岸に渡ってしまうので食べないように気をつけてください。
2021.09.22
中秋の名月
今日は残念ながら雨でしたが、昨日はよい天気でした。
中秋の名月ということで非常にきれいな月が顔を見せていました。
今年はちょうど満月の日と重なっておりきれいな丸い月でしたね。
実は8年ぶりとのこと、来年、再来年は満月ですがその後は30年後のようです。
写真を撮ってみましたが、スマートフォンでは光が強く、月の模様が映りませんでした。
実際には月のウサギ模様がしっかり見えました。
月見といえばススキと団子がそばにあるイメージです。
なので、月見団子を買ってきてお月見をしました。
ススキは前日山に行ったときにとってくればよかったのですが、花粉症がひどくなるので断念しました。
よい風が吹いており、コオロギの鳴き声の中月明かりに照らされながらお団子を食べていると透明になれる気がしますね。
来年もきれいな月をみれるように頑張っていきたいです。
2021.09.15
秋の植物-コムラサキ
9月も半ばに入りました。
朝方は大分涼しくなってきました。木々の色も次第に緑から変化しつつあります。
その中に当院の庭の東側に紫色の実がなりました。
公園などでもよく見かける植物、「ムラサキシキブ」です。
ムラサキシキブといえばまず思い浮かぶのが源氏物語の著者の香子さんこと紫式部ですね。
実際にムラサキシキブの語源もその江戸時代の植木屋さんが紫式部になぞらえてつけたという説があります。
ほかに紫の実が重なり合うところから「紫敷き実(むらさきしきみ)」がなまったものとされる説もあるようです。
様々な種類があるようですが、これは実の小さな「コムラサキ」と思われます。
シソ目クマツヅラ科ムラサキシキブ属の植物で日本全国に分布していおり、観賞用としてあちこちに植えられています。
花が咲いた後、最初は白-緑色の実がなり、次第に紫色に染まっていきます。
3mmくらいの紫色の実が集まってなっています。花は意識したことがなかったですが小さい薄紫の花がさくようです。
毎年実がなってから気づいてしまうので、来年は花もしっかり見てみたいですね。
2021.09.08
夏の終わり
9月に入ってから急に涼しくなってきました。
あれほど聞こえてきていた蝉の声も全く聞こえなくなりました。
代わりにコオロギなど、秋の声が増えてきました。
思い返してみると、今年はヒグラシの声を聞いてない気がしますね。
庭にはたくさんの蝉の抜け殻が木々に下がっておりもの悲しさを感じます。
さて、コロナワクチンの話で世の中はいっぱいですが、そろそろインフルエンザワクチンが始まる季節でもあります。
当院では例年は10月下旬頃から行っています。
まだ予約は開始していませんが、今年は昨年よりもインフルエンザのワクチンの数が少ないとの話もあり、どのくらい確保できるのかドキドキしています。
また、コロナワクチン接種から2週間は空けなければいけませんので、ファイザー製のワクチンの場合は2回目が終わらなければインフルエンザワクチンが打てないことも注意が必要です。
予約を開始しましたらHPでも告知しますのでよろしくお願いします。
それでは、皆様、気温の変動に体を壊さないようにお過ごしください。
2021.09.01
夏の花-アサガオ
8月もついに終わり9月になりました。
ここからどんどん秋に近づいていくのでしょうね。
ワクチン接種も進んでおり、渋谷の件などをみても皆様の関心の高さがうかがえます。
当院にもワクチンについてのお問い合わせをいただいておりますが、残念ながら現在予定されている枠はすべて埋まっております。
今後のワクチンの納入についてはまだ未定な状態です。
さて秋になってしまいましたが今回はアサガオです。
なかなか咲きませんでしたがようやっと咲いてくれました。
種類としてはヒルガオ科、サツマイモ属です。
日本に広く普及しており、夏になるとそこかしこで見かけられ、小学一年生の夏の宿題としても皆さんの印象に残っているかと思います。
その名前の通り朝になるときれいな花を見せてくれています。
奈良時代末期から平安時代にかけて遣唐使が日本に持ち込んだとされ、多種多様な種類があります。
当初は下剤などの薬用の植物として扱われていたようですが、江戸時代に品種改良を重ねられ種類が増えたようです。
花言葉はそのつるが巻き付いていく様子から「愛情」、「結束」などがありますが、実は色によっても変わるようです。
調べてみると様々な種類があって驚きました。
アサガオは一般的な種類しか見たことがないので、いつかいろんな種類のアサガオも見てみたいものです。
2021.08.25
夏の花-ホウセンカ
残暑も厳しいですが激しい雨も多く、勢いよく降っていた雨がすぐやんでしまって日差しがさしたりと忙しい天気が続きます。
コロナの感染も多くなっていますが、集団接種も進んでいます。私も今まで市の集団接種に3回ほど手伝いに行きましたが、毎回大勢の人がいらっしゃっています。
日々接種が進んでいることを実感しています。
今回はホウセンカです。
ツリフネソウ科の植物で東南アジア原産の花で、7-9月に開花します。
夏の暑い日に赤い花を咲かせているイメージがあります。
様々な種類があり、自分のイメージでは一重のものが多いのですが、これは八重咲きのものです。
漢字では「鳳仙花」とかき、花弁が鳳凰の姿に似ているところから来ています。
別名に「爪紅」とも呼ばれるようです。花弁を染料にして爪をぬっていたことから来ています。
実に触れるとはじけて種が飛び散るのは有名ですね。
このことにちなんで花言葉は「私にふれないで」、「せっかち」などです。
子供の頃は面白がってよくつついて遊んでいたことを思い出してしまいます。
結構強引につつたりしていたので、今考えるとホウセンカには悪いことをしてしまっていましたね・・・
2021.08.22
アキノキリンソウ
お盆が終わった途端にまた暑くなってきました。雨も増えており、突然の大雨に驚くこともしばしばです。
とはいえ、夜にはコオロギの声が聞こえてきたりと着実に秋に近づいていることも実感できます。
今回はアキノキリンソウです。
キョウカノコが咲き終わった後に黄色い総状の花を咲かせています。
漢字では「秋の麒麟草」と書き、名前の通り8-11月に黄色い花をつけます。
名前の由来は、キリンソウという植物がありまして、これに花が似ていて秋に咲くのでこの名前になったようです。
キリンソウはベンケイソウ科にあたりますが、これはキク科の植物ですので、種としてはかなり違うものの様です。
キリンソウの名前は様々な説があり、花の形から「黄輪草」とされたという説や麒麟のたてがみや角に似ているからという説もあるようです。
北海道から九州まで広い範囲に自生しておりよく見かける花なのではないでしょうか。
漢方では薬としても使われ、利尿、膀胱炎、風邪の咽頭痛、頭痛などに効果があるようです。
徐々に秋に近づいており、気温の変化で体調を崩す方も増えてきてます。
風邪など引かないように気をつけてくださいね。
2021.08.16
花火大会
お盆も終わってしまいました。
今年はコロナ感染が急拡大しておりどこにも行かずに自宅で過ごしました。
そんな中外から「ドーン、パパッ」という音が外から聞こえてきたので外を見てみると花火が上がっていました。
曜日の感覚も薄れていましたが14日に花火大会が行われていました。
19時から20時半まで、雨の中でしたが色とりどりの花火がしっかりと上がっていました。
今年は1万発ほどとのこと、昨年は上がらなかった分今年は盛大に打ち上げられていました。
残念なことは風のため風下になってしまったので後半は煙に隠れて見えなくなってしまったことですね。
休みも終わり、明日から通常運転に戻ります。よろしくお願いします。




2021.08.11
夏の花-ムクゲ
暑い日が続いていますね。
関東のほうでは気温が40℃に届いたところもあるというので驚きです。
少し前までは37℃をこえたことに驚いていた気がしますが、年々気温の上昇が目立ってきてますね。
熱中症のリスクも上がるので、皆さん涼しくしてお過ごしください。
今回の花は「ムクゲ」です。
アオイ科フヨウ属の植物です。
庭の西側の方に咲いています。夏から秋にかけて咲く花で、白やピンクなどの色があります。
当院に咲いているのは白地に中心が赤い宗旦木槿と思われます。
原産は中国で、日本には平安時代に渡ってきたとされています。
昔からいろいろな家庭の庭や公園でよく見かけられる植物で、夏になると青い空を背景に白い花がよく生えます。
次々と花が咲いているのでずっと咲いているようにも見えますが実は1-2日くらいでしぼんで新しい花が咲いているのだそうです。
皮や蕾は薬としても使われるようで昔から人々になじまれている植物なのですね。