ブログ
2021.03.31
春の花③
本日は3月31日ということで、今日は今年度も最後となります。
先日おみせした梅も一気に咲き始めもう8分咲きくらいになりました。
昨年の4月1日から父親と一緒に診療所で働き始め、無事1年を過ごすことができました。
これも皆様のおかげです。ありがとうございました。
これからもよろしくお願いたします。
さて当院の庭の木々もどんどん蕾がふくらんできています。
椿ももう少しで咲きそうですが先駆けてさいたのはアセビでした。
アセビはツツジ科の植物です。別名を「馬酔木」ともいい、馬が葉を食べると毒にあたって酔っているようにふらふらするということが由来になっているようです。
当然人間にも危ないようですね。
小さな白い袋状の花がたくさん集まってます。最初ドウタンに似ていると思いましたが同じツツジ科の仲間だったとのことで納得です。
ドウタンよりも茎が短く、花が密集して賑やかな感じですね。数えてみると40個位ありました。
あまり知りませんでしたが万葉集にもでてくるようで昔から日本にある植物のようです。
日本のアンドロメダともいわれ、このためか花言葉は「犠牲」、「献身」とのことです。
来年度もいろんなことがあるとおもいますがアセビの花のように「献身」の気持ちを忘れずに働いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
2021.03.29
春の花②
もう少しで今年度も終わろうとしています。
山形はコロナウイルス感染症が広まり大変な状況になっています。
ワクチンの摂取に期待したいところです。
当院でもワクチンを投与できるように申請はしていますが、予約は山形市の指示で一斉に始まると思われ、肝心のワクチンが山形に入ってこないのでなかなか始まらないようです。
そのような中、季節はどんどん春めいてきています。週末は雨で少し寒くなりましたが、我が家の梅がようやく開花しました。
冬の間枯れてないかと心配していましたが、3月になってからつぼみがどんどん大きくなってきて咲くのをたのしみにしていました。
まだ満開にはほど遠いのですが、少し明るい気持ちになります。
今年は花見にも行けませんのでこうして庭先で春を感じられるのはありがたいですね。
医院の梅はまだ咲いてはいませんがこれからさいていくのが楽しみになります。
2021.03.16
春の花
東京では桜が咲き始めたようです。
山形はまだ風は冷たいですが、梅の蕾がもう少しで咲きそうなくらいに桃色になってきました。
ついこの間まで蕾だった福寿草が開花しました。
小さな黄色い花が一生懸命咲いています。
この福寿草、以前に患者さんにいただいたもののようで、いただいて以降毎年顔をみせてくれています。
患者さんとのつながりを大切にしている当院としては非常にうれしいものです。
庭をみるとほかにも色々な植物の芽がニョキニョキと顔を見せてくれています。
春の風が吹いていますね。
2021.03.05
春の足音③
3月も数日すぎ梅のつぼみも膨らんできました。
山形でも来週から医療従事者のワクチン接種も始まるようです。
医師会でも高齢者に対する接種の説明会が先日行われ少しずつ前に進んでいるようです。
イベントとしては桃の節句が終わりました。
私は男兄弟しかいなかったのでとんと縁のなかったイベントでした。
先日つぼみだった、ふきのとうも開花してきました。
このままあたたかくなるとよいですね。
ただ、あたたかくなるにつれ花粉も舞ってくるので花粉症の身としては辛くもあるですが・・・
2021.03.01
春の足音②
2月がすぎ3月になりました。
先日のふきのとうに続き福寿草もつぼみをつけました。
どんどん春が近づいてきていますね。
福寿草はキンポウゲ科の花で別名を「元日草」といいます。
雪がとけ春が近づくと黄色い花をみせてくれます。
見かけると春がきたのだなあ、と実感しました。
日本には4種類が自生しているようですがこれはどれなのでしょうか。
実はこれにも毒があるようです。皆さん食べないようにしましょうね。
ここからどんどん暖かく春っぽくなっていくのでしょう、楽しみですね。
2021.02.21
春の足音
2月も後半にはいりました。
雪も一段落してそろそろ暖かくなりそうですね。
コロナのワクチン接種の話題があがっています。
当院でも投与できるように申請などしていますが、
まだ、予約方法や各診療所に配られるワクチンの量や、投与するときの体制などは明確には決まっておらず、検討しなければならないことは多いようです。
そんなこんなでバタバタしている毎日ですが、ようやく春の足音が聞こえてきました。
東京ではもう梅が咲いているようですが、それはまだ先の話。
雪が溶けてきた庭に出てみると雪に押しつぶされた草の間に若草色の丸いものがヒョッコリ顔をみせていました。
ふきのとうです。(分かりにくいと思いますが・・・)
まだ花は咲いていませんがしっかり春の訪れをつげるように芽が出てきています。
やっと冬が終わり春が来とおもうとほんわかと温かな気持ちにさせてくれます。
また毎年雪に負けず出てくる姿をみると、頑張ろうという気持ちになります。
もっと暖かくなって、早く花をみせてほしいものですね。
2021.02.03
節分
昨日は節分でしたね。
皆さんも御自宅などでまめをまかれたでしょうか?
私も豆まきをして恵方巻きを食べました。
我が家では毎年恒例の行事としていますが、今年も色々な鬼がでていってくれればよいという思いをこめて豆をまきました。
今年の節分は2月2日ということで例年よりも1日はやいものとなっていました。
最初に聞いたときには「えっ」と思いましたが潤年のさらに周期の大きいものと聞けば納得です。
1897年以来124年ぶりのできごととのことですが潤年のように規則的に行われるものではないので分かりにくいですね。
来年は2月3日に戻りますが、2025年にはまた2月2日になるようです。
ところで、子供のころ節分といえば、豆まき、柊と鰯の頭というイメージでした。
そこに恵方巻きがいつの間にやら加わってきて、今では普通に皆食べています。
恵方巻きはいつからうまれたのでしょうか。
ちょっと調べてみましたが正確な起源ははっきりしていないようです。
大阪発祥の風習で全国的に広がったのは1998年頃からのようです。確かに2000年くらいに初めて知ったような記憶があります。
太巻きを黙ってひたすら食べきるということで量も多く、最初に食べたときはなかなか大変なものだと思っていました。
もともとは太巻きで具材も7種だったのですが、今では様々なバリエーションがあり、量も少ないハーフサイズもでてきて大分食べやすくなりました。
今ではどんなものがでたかチェックするのも楽しく、節分の風物詩としてかかせないものになっています。
時代とともに風習は少しずつ変わっていきますが、根本にあるのは人々の幸せを願う気持ちと思います。
その気持ちを忘れないようにしていきたいものです。
2021.02.01
続、鬼滅のSL
2021年もあっという間に1月が過ぎ去り2月になりました。
おかげさまで最初の一月を無事にすごすことができました。
今週は寒い予報がでています。我が家も車のバッテリーが寒さでとまるといったトラブルがおきました。
皆さんもスリップなど事故をおこさないようにお気をつけください。
さて、先週のことですが、以前紹介した第二公園のSLが変わったとききました。
どのようにかわったのでしょうか。12月には藤の花のライトアップされ、1月にも追加されるとは一月毎に何か追加されるのでしょうか。
期待していってみました。
遠目からは
だいぶ明るくなりました。天井に星のようにきらめくライトが数多くちりばめられ、柱には夜空のような青いライトがまきつけてあります。
じつは柱にも炭治郎の羽織の模様があしらわれています。
近づいてみました。
線路には夢の国に続くかのように、虹色にかがやくライトが配置されタイヤが反射してきれいです。
側面には煉獄さんに由来するのか赤と黄色の炎がゆらめいています。
さらにSLの正面についているライトが点灯しています。SLっぽくて非常によいです。期間が終わってもこれは残してほしいですね。
まさに「無限」であり「夢幻」でもあり非常に幻想的な雰囲気をかもしだしています。世代的には999も思い出してしまいます。
突然の電飾追加で驚きましたがこういうサプライズはうれしいですね。
今後の展開はあるのでしょうか。期待してしまいますね。
お時間があればぜひみにいってみてください。
2021.01.29
新しくなったトイレです
トップページでも紹介しているように当院のトイレの改装工事が終了しました。
駐車場に仕材をおくためのテントを設置していただき2週間で施工していただきました。
すごい変わりましたので、具体的に御紹介したいと思います。
まず洗面所です。
写真にすると暗くなってしまったのですが実際はもっと明るいです。
まず、洗面所へ入る扉がなくなりました。そして壁紙が明るく白を基調としたストライプ模様になりました。
鏡も大きくなり上下にライトがついています。洗面台はもちろんセンサーで水がでるようになっています。
洗面台の下には木目調の引き出しがつきました。
むかって右にはトイレに続引き戸がついています。そちらに行ってみると、
ちょっとシャープな感じの男性用小トイレがあります。もちろんセンサー式で前に立った時と離れて少ししてからの2回水が流れるようになっています。
今までタイルだった床、扉は木目調になりました。写真にはうつっていませんがトイレに入る所にあった段差がなくなってつまづくことがないようになっています。
右には洋式トイレがありまして
こちらも一新されました。壁紙、床は一緒ですが手摺りがついて立ちあがりやくすなってます。
トイレも自動水洗になっています。自動で水が流れますので驚かないでくださいね。
あとわかりにくいですが、上のほうに荷物をおくための台がついています。
今回の改装はコロナ対策として自動水洗にすることがメインだったのですが、全体的にかなり明るく、きれいな印象になったとおもいます。
今までとはまったく別の場所になったようです。なにかご不便があれば教えていただければと思います。
よろしくおねがいいたします。
2021.01.11
初市
昨日は1月10日でした。
例年では初市の日で、当院の前の大通りも屋台がならんで賑やかになるのですが、今年は規模縮小ということで静かな一日でした。
そのかわり夜間に花火があがりましたね。
30分間霞城公園の空にたくさんの大輪の花が咲いていました。
非常に寒かったのですがベランダからみていました。
途中ベランダのドアが凍って動かなくなるというハプニングもありましたが、
様々な花火があがりあっという間に時間がすぎていきました。
昨年は様々なイベントが中止になった分、今回の花火には例年よりもより思いがこめられているのでしょう。
例年とは異なる一年にはなると思いますが今年は良い年になるといいですね。
ところで、昨日から当院ではトイレの改装工事が始まりました。
業者の方にも一生懸命考えていただいたのできっとより快適な空間ができると思います。
2週間後には完成するのでそれを楽しみにしたいと思います。
その間は御不便、ご迷惑をおかけすると思いますがどうかよろしくお願いいたします。

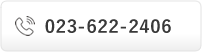
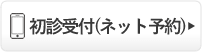
.JPG)










