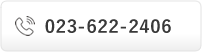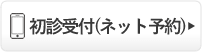ブログ
2022.12.29
仕事納め
29日の診療も無事終わり、今年の診療を終わることができました。
今年も色々なことがありましたが無事に年を越せそうです。
年末年始はまた寒波が来るようで、本日も雪がちらついていました。
去年は28日には大雪が降っていましたが、今年はそこまでは降りませんでした。
街中の雪は少ないと良いですね。
寒くなり、風邪を引いている人も増えてきました。
東京ではインフルエンザの人も増えてきているようです。
これから山形でも増えてくると思われますので皆さん気をつけましょう。
来年の診療に備えてこれから大掃除です。
今年も仕事納めの日を無事迎えられたのは、来ていただいた患者さん、診療所のスタッフの方々のおかげと思います。
ありがとうございました。
2022.12.25
クリスマス
今年の12月は雪が非常に多いですね。
クリスマスイブも寒波が来て吹雪いていました。
道路も凍ってしまい、早速転倒してお尻をしこたま地面に打ち付けてしまいました。
皆さんもけがしないようにお気をつけください。
例年、2月頃が一番積雪が覆い印象ですが、今後どうなるのでしょうか。
雪かきのことを考えると憂鬱になります。
さて今日はクリスマスですので、いやなことは忘れて楽しく過ごしたいと思います。
メリークリスマス!
2022.12.02
初雪
いよいよ12月になり今年もあと少しとなりました。
12月になった途端に急に冷え、ついに今日は町中でも雪が降りました。
積もりこそしませんが本格的に冬に突入した感があり、雪かきなどすこし憂鬱な気持ちもあります。
町の中で少し不思議な光景を見かけました。
雪が舞う中、桜が咲いています。
冬の桜といえば啓翁桜が有名ですが、あれは枝を暖めて咲かせるもの。
普通に外に生えている桜が咲くものではありません。
ということで少し調べてみましたが、冬桜いうくくりの冬に咲く桜が何種類かあるようです。
冬にだけ咲くカンザクラ、ヒマラヤザクラなど
二期咲きのフユザクラ、ジュウガツザクラなど
晩秋-早春にさく園芸品種のカンザクラ、カワヅザクラなど
と結構な種類の桜が当てはまり、日本全国にあるようです。
私は山形大学医学部で咲いているのを見かけたのですが、今まで全く気づきませんでした。
何という桜なのでしょうね。

2022.11.24
秋の草花-ノコンギク
昨日は勤労感謝の日でした。
残念ながら天気は雨でした。昨年も雨でしたのでこの時期は雨に見舞われやすいのかもしれません。
紅葉した葉もあっという間に散ってしまいました。
勤労感謝の日はもともとは「新嘗祭」というもので、その年に採れた作物を神様に捧げ感謝する日だったようです。
昔の人は様々なものに感謝して生活していたようです。
私もそのような気持ちを忘れないようにしたいですね。
さて、全国的にコロナ感染症が増えてきています。
行動制限をかけないような方針のようですが、一方でワクチン接種に関しては推進するために色々な動きがありました。
大きなものとしてはオミクロン株のワクチンを普及させるために4回目終了した方は3ヶ月あければ5回目のワクチン(オミクロン株対応)を打てるようになりました。
今皆さんの手元にも接種券の案内が届いていると思います。
各クリニックで行う個別接種は1月までという話もありましたので、個別接種を希望される方は急いだ方が良いかもしれません。
さて、今回は「ノコンギク」です。
キク科の花で、8-11月くらいに咲きます。
これぞ菊、という感じの外見です。地下茎があるので群落を作りやすく、まとまって咲いていることが多いです。
様々な色があるようですが、当院のものは鮮やかな紫色で、小さな可愛い花が風に揺れているのが目に入ります。
花言葉には「長寿と幸福」とあり、派手ではないですがみてると小さな幸福を感じられる感じがします。
この花がさくと秋も終わりという感じがします。
2022.11.13
秋の草花-ホトトギス
早くも11月も半ばを過ぎようとしています。
かなり冷えるようになりました。
寒さのせいかコロナウイルスの感染者も増えてきました。
11月7日からB.A.4,5対応のワクチンとなり、接種の間隔も3ヶ月に短縮されました。
クリニックの個別接種も1月までとの連絡も来ました。
以後は集団接種となるようですので、個別接種を希望される方は急いだ方が良いようです。
この時期になると庭の西側に紫色の変わった形の花が毎年咲きます。
今年も紫色のはなが群れをなして咲いています。
名をホトトギスといいます。
ユリ科の花で、花弁の斑点が鳥のホトトギスの胸の模様に似ているためこの名前になったようです。
ホトトギスの口に似ているとかではないのですね。
葉に油を垂らした染みの様な斑点があることがあり「油点草」という別名もあるようです。
調べてみると思っている以上に種類がたくさんあり驚きました。色も黄色のものもあるようです。
内花被片3枚、外花被片3枚の6枚の花弁の中に放射状に分かれる花柱が立ち非常に星のような特徴的な形をしています。
秋の草として俳句やお茶の席などに用いられます。
道ばたではあまり見かけない花ですが形がかなり印象的ですので一度見ると忘れないかと思います。
皆さんも探してみてください。
2022.11.08
皆既月食
昨日からコロナワクチンがオミクロン株のB.A.4,5対応に切り替わりました。
また感染者数が増えているようですので気をつけないといけませんね。
11月8日は皆既月食がありました、しかも天王星が月の後ろに隠れるという天王星食も一緒におこるという珍しいものでした。
なんと1580年以来の出来事となるようです。
日中は曇り空で、月が出ることはなさそうな雰囲気でしたが夜になると見事に月が出てくれました。
隠れ始めるところから見たかったのですが、残念ながら本日は医師会のオンライン受付の説明会がありました。
説明会終了時に空を見上げてみると、すでに月全体が隠れて赤銅色の鈍い光を放っていました。
月食をBlood moonというようですが、まさに血染めの月という色合いでした。
個人的にBlood moonには苦い思い出があったりするのですが、そんなことを思い返したりしていると、次第に月が影から出てきていつもの白い光が戻ってきました。
月食自体は何回か見ていますが、いつ見ても神秘的な光景に感動を覚えます。
残念だったのは天王星が認識できなかったことですね、テレビで拡大しているものを見るとわかるのですが、肉眼では難しかったようです・・・
2022.10.11
秋の草花-ギンモクセイ
秋も深まってきました。
あちこちの庭先からもキンモクセイのよい匂いが漂って来るようになりました。
今回はキンモクセイに似ているヒイラギモクセイです。
庭の西側、お蔵の前で白い小さな花を咲かせています。
今年はキンモクセイよりも早くこちらの方が開花しました。
ヒイラギとギンモクセイの雑種と考えられていて、両者の特徴を備えています。
9-10月頃に開花し白いギンモクセイのような花を咲かせています。
残念ながら香りはキンモクセイほどではないですが、同じようなよい香りです。
葉はヒイラギ似てギザギザしており、ギンモクセイとの違いは一目瞭然です。
ただし本物のヒイラギほどはとげとげしておらず、光沢もありません。
ぱっと見はわかりにくいですが、よく見ると区別できるかと思います。
大分冷え込むようになってきましたので風邪など引かぬよう気をつけてお過ごしください。
2022.10.10
秋の草花-フジバカマ
に冷えてきましたね。
暖かくして体調を崩さないようにしましょう。
今日はスポーツの日ですね。
あいにく朝から雨が降っており、グラウンドはぬれてしまっていました。
さて秋も深まり、今年もフジバカマが咲きました。
キク科フジバカマ属の植物で10月から11月頃に花を咲かせます。
秋の七草の一つで白っぽい小さなふわふわした花がたくさん集まって咲いています。
秋の七草とは春の七草に比べるとメジャーではないかもしれませんが、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの七つです。
万葉集にある山上憶良の歌からとられており、
「秋の野に 咲きたる花を 指折り かき数ふれば 七草の花」
「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」
の歌からとられています。
今NHKで放映されている、鎌倉殿の十三人にもでてくる源実朝もフジバカマを題材にして歌を詠んでいます。
「藤袴 きて脱ぎかけし 主や誰 問へどこたえず 野辺の秋風」
とある姫君がはいていた藤色の袴が花になったという伝説もあり、「藤色の袴」と「藤袴」をかけて詠んだのかと思います。
どんな情景を想像して詠んだのかを考えると面白いですね。
昔から日本に存在したフジバカマですが、今は環境省のレッドリストに載っており、準絶滅危惧種に指定されています。
護岸工事などにより数が減ってしまったようです。
2022.10.09
秋の草花-コムラサキ
10月に入り急激に涼しくなってきました。
インフルエンザワクチンの予約は埋まっていますが、コロナワクチンの予約はほぼ埋まらないですね。
まずインフルエンザからという人が多いのかもしれません。
同時に接種可能とはいえ、フェイザー社のオミクロン対応のワクチンは副反応の率が上がっているようですし、別日にしたいと考えるの人は多いのかもしれません。
それに、同時接種を行って、もし重篤な副反応が起きた場合はどちらが原因なのかわからなくなってしまうのも問題になるかもしれません。
さて、当院の庭の東側に紫色の実がなりました。
公園などでもよく見かける植物、「ムラサキシキブ」です。
ムラサキシキブといえばまず思い浮かぶのが源氏物語の著者の香子さんこと紫式部ですね。
実際にムラサキシキブの語源もその江戸時代の植木屋さんが紫式部になぞらえてつけたという説があります。
ほかに紫の実が重なり合うところから「紫敷き実(むらさきしきみ)」がなまったものとされる説もあるようです。
様々な種類があるようですが、これは実の小さな「コムラサキ」と思われます。
シソ目クマツヅラ科ムラサキシキブ属の植物で日本全国に分布していおり、観賞用としてあちこちに植えられています。
花が咲いた後、最初は白-緑色の実がなり、次第に紫色に染まっていきます。
3mmくらいの紫色の実が集まり葡萄のようにみえます。
あちこちで見かける印象ですが、実はあちこちの県でレッドリストにのっているようです、全く信じられませんが・・・
2022.10.08
十三夜
本日10月8日は十三夜でした。
あまり聞かない言葉ですが、旧暦の9月13日の夜のことで十五夜と並ぶ名月とされていています。
十五夜が中国で始まった風習なのに対し、十三夜は日本で生まれた風習です。
諸説ありますが平安時代の醍醐天皇が始めたという説が有力です。
満月から少し欠けた月を愛でるのは日本独自の風習で、十五夜とセットで楽しむものとされ、一方しか行わないのは「片見月」といわれ縁起が悪いものとされています。
豆や栗が収穫できる季節であり、別名「豆名月」や「栗名月」ともよばれます。
今年は十五夜に続き十三夜もきれいな月が見えました。
確かに十五夜に負けず劣らずの月で、昔から愛されていたのも頷けます。
昔の人も収穫が終わった後、この月を見て一年の恵みの感謝の気持ちと、来年への気持ちを改めていたのでしょうか。
今年は月が明るすぎてスマホではなかなかうまくとれませんでした。
少し雲がかかるとハレーションが強く真っ白になってしまいました。
お団子を・・・と思いましたが、今年は買い逃してしまい、目で楽しむだけとなってしまいました。残念です。