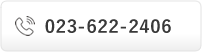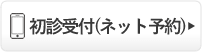ブログ
2023.05.10
春の草花-ボタン
3日間続いた植木市も今日で最終日ですね。
昨日行ってみましたがすさまじい人出の多さで驚きました。
久しぶりに出店がたくさん並んでいる景色を見た気がします。
薬師祭植木市として、日本三大植木市の一つとされており、山形市では大規模の祭りの一つです。
最上義光が始めたとされており、歴史があるお祭りですね。
当院の庭では牡丹が咲き始めました。
植木市で買った牡丹であり、これが咲くと植木市の時期が来たと思います
様々な色がありますが、大きな花びらを幾重にも詰め込んだ、絢爛豪華な花です。
昨年は白でしたが、今年の写真は赤紫の艶やかなものです。
中国が原産で日本には8世紀頃からの記録が認められ、枕草子に記載されているのが最初とのことです。
昔から人々に好かれる花だったのか、牡丹灯籠や八犬伝など様々な物語にもモチーフとして使われています。
南総里見八犬伝では犬士の証として扱われており、ツバキと同様何かしら霊的なものを感じる花ですね。


2023.05.08
発熱外来
5月9日からコロナウイルスが5類に分類されました。
同時に発熱外来もすべての診療所で行うようになりました。
当院での最大の問題だったのは導線の分離でした。
患者さんが使う入り口が1カ所しかなく、発熱している患者さんが待機できるスペースに行くまでに玄関、待合室、廊下と通らなければいけないのでどうしても導線が分離できず、どうしても発熱外来を行うことができませんでした。
5類に分類された以降も導線は可能な限り分けるようにという指示にもかかわらず発熱外来はすべての診療所で行うようにという指示だったのでどうしたものかと思っていましたが、県の医師会に質問したところ、導線は一部かぶっても、途中しゃべらずすれ違うことは問題ないという回答をいただきましたので行うこととしました。
テレビなどでなぜ発熱外来を行わない施設があるのか、という話は出たりしますが、医院の構造上、導線が完全に分けられないのでやりたくてもできない、という診療所は多かったと思います。
発熱外来は開始しましたが、なるべく他の人との接触を避けるために時間を11時半から12時までとしています。
車でご来院される方は車で待機していただきます。
また検査は抗原検査のみとなります。
もし来院される際は事前にご一報いただければ助かります。
また、医院には様々な基礎疾患を持っている人がいらっしゃいますので来院される方はマスク着用をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2023.05.07
春の草花-アケビ
今日でGWも終わりですね。
後半は残念ながら雨続きの天気でした。
能登半島付近では地震があり、雨で被害が拡大しないことを祈るばかりです。
今回はアケビです。
実が有名で花の印象は薄いのですが、濃い紫色でぱっと見だと黒く見えます。
あまり見ない色ですし、形も独特の形をしています。
アケビ科の植物で、北海道を除く全国に生息する植物で、山では周りの木に絡みついて大きくなっていきます。
雌雄同株ですが雄花と雌花がに分かれています。
雄花には6本のおしべが、雌花には3-9本の雌しべがあり、昆虫を介して受粉するようです。
しかし、蜜を持たないので、どのように昆虫を呼び寄せているかはよくわかっていないようです。
薄紫色の実がなり、熟すと果皮が紫色になり、中央が裂けて内部の果肉が見えるようになります。
山形では実だけではなく皮も食べるとTVなどで紹介されたりしてます。
少し苦みがあるので子供は苦手かもしれませんが、慣れるとおいしいですね。
種子にはスミレのときにも出てきたエライソオームがついており甘くて鳥や動物に運ばれて繁殖していくようです。
漢方では薬としても用いられ、実も皮も食べれて栄養もある、蔓でかごなどを作ったりと非常に生活に役立ってくれている植物ですね。


2023.05.06
春の草花-スミレ
昨日はこどもの日でした。
当院の前の通りでは働く車が大集合していました。
天気も良く久々のイベントということで賑わっていたようです。
今回はスミレです。庭の西側に生えている樫の木の根本に咲いています。
3-5月頃に紫色の小さな紫色の花を咲かせる春の代表的な花の一つです。
春の季語としても扱われ、日本人に親しまれてきました。
語源は大工さんの使う「墨入れ」に形が似ているからということですが、墨の黒い色からは想像できないきれいな色ですね。
スミレは沢山の種類(150種類以上と言われているようです。)があって正式に同定するのは難しいですね。
当院に咲いているものは「マルバスミレ」ではないかと思われます。
日本では本州、四国、九州に分布し、北限が青森、南限が屋久島まで存在するようです。
北海道には咲かないんですね。知りませんでした。
スミレの花は砂糖漬けにしたり、葉を天ぷらにしたりするようですが、根には毒を含む種も有るようで注意が必要です。
この後、種子がなりますが、種にはエライオソームと呼ばれる蟻などが好む成分が付着しており、これにより蟻などの生物に遠くまで運んでもらって増えていくようです。
生きていく工夫が独特で面白いですね。

2023.05.04
春の草花-ドウダンツツジ
GWも半ばが過ぎました。
各地は観光客でごった返しているようですね。
5月になると白い花が咲きます。
ドウダンツツジです。
今年は少し花の数が少ないきがします。
名前からもわかるようにツツジの仲間で4月から5月にかけて咲きます。
秋には紅葉して真っ赤な葉になります。
公園にもよく植えてあるのでよく見かける植物です。
花言葉は「節制」、「上品」といった言葉で白いきれいな花ですが厳しい環境にも耐えられるという意味が込められています。
アセビと花はよく似ていますがこちらは毒がなく無毒な植物です。
「ドウダン」は花が枝分かれした様子が昔の夜間の明かりに使われた灯台に似ているところから「トウダイ」から転じてつけられたようです。
灯台は普段私たちが思いつく海にたっている灯台ではなく、3本の棒を結わえてねじり、その上に油の入った皿を置いたものです。
時代劇では部屋の明かりとしてよく見かけますね。
このため漢字では「灯台躑躅」と書きます。
ほかにも「満天星」(まんてんせい)とも書かれます。
暗がりで見ると天に白い星がちらばっているようにみえてきれいですね。


2023.05.01
春の草花-オダマキ
今日から5月です。
日中は暑かったですが、夕方からは風が吹いてきて寒くなりましたね。
このような寒暖差が激しいときは調子を崩しがちですので気をつけてください。
今回はミヤマオダマキです。
通常のオダマキより小型のオダマキです。
昨年よりも大分早く花をつけました。やはり今年の気温が高い性なのでしょうか。
桜前線も例年より一月ほど早く上昇しているようです。温暖化と考えると少し怖いですね。
オダマキはキンポウゲ科の植物で中部地方から北海道にかけて生息する高山植物です。
10cmくらいの高さでうつむき加減に花をつけます。
花はだんだんと起き上がってきて最終的に上向きになって実をつけるようです。
毎日表情が変わるので違う花を見ているようで飽きないですね。
花弁の形も特徴的で、基部から萼の間を抜けて距が伸びています。
名前の由来は「苧環(オダマキ)」という麻糸を巻く道具が花の形と似ていることからついたようです。
なるほど、上に飛び出た距の部分が糸を巻き取る棒の部分にそっくりです。(写真には写ってないですが・・・)
昔の人の名前の付け方には本当に感心させられます。
これは以前、患者さんからいただいたものです。今年も見事な花を咲かせてくれました。
ありがとうございます。

2023.04.30
春の草花-シャクナゲ
4月ももう終わりです。
GWに入ってあちこちに旅行に行く人も多いのではないでしょうか。
4月最後の今日は風が強く肌寒い日でした。
昨年の4月30日は雪が降りましたが、そこまでは寒くならなかったですね。
今回はシャクナゲです。
ツツジ科の植物で、ツツジに似た大きな花を咲かせます。
4-5月に咲く花で、登山をしていると岩場の間から顔を出しているのをよく見かけます。
高いところで急にこんな大きな花に出会うと、ドキッとしますね。
元々は高山植物で危険なところにきれいに咲くため「高嶺の花」の語源となっています。
同じ理由で花言葉も「危険」、「警戒」「威厳」、「荘厳」などと言ったものになっています。
漢字では「石楠花」と書きます。呉音読みの「シャクナンゲ」が転じたものです。
中国から輸入されてきたとき、漢方で使われる「石花」と間違えられたためこの漢字となったようです。
間違いから来ているとはいえ、岩の間から生えている姿を見るととても似合っている字ですよね。


2023.04.18
春の花-ヤマツバキ
4月も後半に入ろうとしていますが、まだ朝や夜は肌寒い日が続きます。
今回は「山椿」です。
ヒメツバキのピンク色も良いですが、ツバキといったら紅ですね。
2-4月に開花して冬のイメージもありますが春の季語になっています。
花もきれいですが、種からは油をとったりと生活にも必要な植物です。
しかし、花びらが散るのではなく、首元から花が落ちるため死を連想させるとして縁起が悪いとされることもあります。
このためかどうかは不明ですが古い椿には霊が宿るとされています。
江戸時代の鳥山石燕の今昔画図続百鬼にも古椿の霊としてあげられるくらいメジャーな霊だったようです。
石燕の絵では庭先に大きな花をつけた椿が書いてあります。
あちこちに椿に関する怪談があるようですが、実は山形にも椿の怪談があるようです。
旅人を蜂に変えてしまい、自らの花におびき寄せて食べてしまうという恐ろしい話です。
黒緑の葉に囲まれた中に紅い花がぽつんと咲いているのを見ると妖しげな雰囲気がして、昔の人が化けると考えたのも納得できる気がします。
ただこの話、場所がわかりません。「山形の会談」という本が発売されたのでよんでみましたが残念ながらのっていませんでした。
山形の化け椿もまだどこかで咲いているのでしょうか。
そして当院の椿もいつか化けるのでしょうか。想像が膨らみます。


2023.04.17
春の花-スイセン
暖かくなったと思いましたが、風が強く冷える日が続いています。
さて、今回はスイセンです。
せっかく黄色い花を咲かせたのですが、風で倒れてしまっていました。
少しかわいそうです。
ヒガンバナ科の花ですが、ヒガンバナとは大きく印象が異なります。
6枚の花弁に見える部分は、上3枚が花弁で下3枚は萼になります。
雄しべと雌しべを囲む筒状の部分は副花冠と呼ばれています。
英語名はNurcissus(ナルキッソス、ナルシス)とよびます。
ギリシャ神話の美少年の名前です。
水に映った自分の姿に恋をして花に変わってしまう、という話で、この花がスイセンとされているようです。
よく見る花ですが、毒草で食べると30分以内に嘔吐、下痢、頭痛がおきて、ひどくなると意識消失も起こってきます。
この時期になるとスイセンの中毒のニュースがでてきます。
花が咲いていればわかりやすいのですが、葉っぱだけだとニラに似ているので、間違われて食べてしまうようです。
匂い(スイセンは匂いなし)や、球根の有無(スイセンは球根あり、ニラは球根なし)で見分けられます。
採取するときははさみで切らずに根っこから引っこ抜くとわかりやすいようです。


2023.04.09
春の草花-アセビ
今日は朝起きたら山が白くなっていました。
暖かくなってきたと思っていたら、いきなりの雪で驚きました。
確かに天気予報では日曜に雪、といっていましたがまさかと思っていました。
こんな時期に雪とは、と思っていましたが昨年のブログを見ると、昨年は4月30日に雪が降っていたようです。
まだ油断はできなそうですね。
今回は「アセビ」です。
アセビはツツジ科の植物です。
小さな白い袋状の花がたくさん集まってます。最初ドウタンに似ていると思いましたが同じツツジ科の仲間だったとのことで納得です。
ドウタンよりも茎が短く、花が密集して賑やかな感じですね。
別名を「馬酔木」ともいい、馬が葉を食べると毒にあたって酔っているようにふらふらするということが由来になっているようです。
実際に葉などには「アセボトキシン」という毒が含まれており、当然人間にも有害で、下痢、腹痛、呼吸麻痺などを引き起こします。
逆にこれを利用して殺虫剤にしていたようで、昔の人の知恵はすごいですね。
人だけでなく、昆虫にもこの毒を利用するものがいます。
ヒョウモンエダシャクと言う蛾の仲間で幼虫の時期にアセビの葉を食べて体内に毒を蓄積させるようです。
アセビは英語名で「Japanese andromeda」ともいわれます。
ギリシャ神話のアンドロメダにならってか花言葉は「犠牲」、「献身」となっています。
ところで、この名前はandromeda(ヒメシャクナゲ)に似ていることが由来のようです。
ではこのヒメシャクナゲの花言葉はというと、「警戒」「危険」です。
なぜ、こうも違ってしまったのでしょうか。