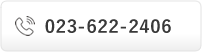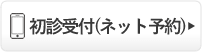ブログ
2022.05.06
春の花-スミレ
5月のコロナワクチンの予約はなかなか埋まりません。
3回目の接種は希望者に行き渡りつつあると言うことでしょうか。
さて今回はスミレです。
春と言えばすぐ頭に浮かんでくる花の一つですね。
様々な色がありますが、紫色が一番好きです。
この色がスミレ色と言われるくらい日本ではおなじみになっています。
庭の西側に咲くのですが、今年は少しすくなめな感じがします。
うまく種をまけなかったのでしょうか。多年草なので同じ場所には咲くはずなんですが・・・
その繁殖方法が特徴的で、数種類の技を持っています。
一つは砲丸投げのようにさやから種を弾き飛ばす方法です。
飛距離は3mもあるようでかなり遠くまで飛ばせるようです。
もう一つは蟻に運んでもらう方法です。
エライオソームという甘い物質を種につけて蟻に巣まで運んでもらいます。
自然の知恵はすごいですね。
来年はたくさんの花を見たいですね。
2022.05.05
春の花ーミヤマオダマキ
GWも終わりに近づいています。
よい天気が続いて暖かくてお出かけ日和ですね。
今回はミヤマオダマキです。
キンポウゲ科の植物で中部地方から北海道にかけて生息する高山植物です。
10cmくらいの高さでうつむき加減に花をつけます。
花はだんだんと起き上がってきて最終的に上向きになって実をつけるようです。
様々な色がありますがこれは白色です。
花弁の形も特徴的で、基部から萼の間を抜けて距が伸びています。
名前の由来は「苧環(オダマキ)」という麻糸を巻く道具が花の形と似ていることからついたようです。
これは昨年、患者さんからいただいたものです。
最初種から育てようとしたのですがうまく発芽せず、結局苗をいただきました。
昨年は花を咲かせませんでしたが、今年は見事な花を咲かせてくれました。
ありがとうございます。
2022.05.03
春の花-ドウダン
GWも始まりました。今年は各種イベントも再開しているようです。
山形では米沢の上杉祭りが再開されて話題になりましたね。
感染対策をして楽しんでください。
今回はドウダンツツジです。
名前からもわかるようにツツジの仲間で4月から5月にかけて咲きます。
公園にもよく植えてあることが多いですね。
アセビと花はよく似ていますがこちらは毒がなく無毒な植物です。
「ドウダン」は花が枝分かれした様子が昔の夜間の明かりに使われた灯台に似ているところから「トウダイ」から転じてつけられたようです。
灯台は3本の棒を結わえてねじり、その上に油の入った皿を置いたもので、時代劇ではよく見かけるかと思います。
このため漢字では「灯台躑躅」と書きます。
ほかにも「満天星」(まんてんせい)とも書かれます。
暗がりで見ると天に白い星がちらばっているようにみえます。
ロマンティックですね。
2022.04.30
春の花-シャクナゲ
今日は朝起きたら雪が積もっていてびっくりしましたね。
まさかこの時期に雪が降るとは・・・
車のフロントガラスにも雪がつもっていました。
今回はシャクナゲです。
ツツジ科の植物で、ツツジに似た大きな花を咲かせます。
4-5月に咲く花で、登山をしていると岩場によく見かけます。
この花をみながら、あと少し、あと少しと思いながら登っていたのを思い出します。
元々は高山植物で危険なところにきれいに咲くため「高嶺の花」の語源となっています。
同じ理由で花言葉も「危険」、「警戒」「威厳」、「荘厳」などと言ったものになっています。
漢字では「石楠花」と書きます。呉音読みの「シャクナンゲ」が転じたものです。
中国から輸入されてきたとき、漢方で使われる「石花」と間違えられたためこの漢字となったようです。
間違いから来ているとはいえ、岩の間から生えている姿を見るととても似合っている字ですよね。
2022.04.28
春の花-椿
当院の正面を飾るピンク色の椿が今年も咲きました。
ピンク色の幾重にも重なる花弁がかわいらしい感じです。
毎年けなげに咲くこの花を見ると、負けずに頑張ろうと思うようになります。
お隣の仙台市で、新たな変異株が出現したとのことです。
4回目の接種の対象者も発表されました。
今後も様々対応すべきことが出てくるでしょうが、情報を逃さず遅れずに行っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
2022.04.24
春の花-スイセン
明日、4月25日から5月分のコロナワクチンの接種予約が始まります。
クリニックで行う個別接種は、3,4月と異なり5月はファイザー社のワクチンのみとなりますのでお気をつけください。
その分配布される本数はさらに少なくなる(130人分くらい)のですが、4月を振り返るとモデルナ社のワクチンは予約定数に達しない日もありましたから
5月の予約はそのくらいでも大丈夫なのでしょうか。
さて、今回はスイセンです。
庭の西側に黄色い花を咲かせています。
ヒガンバナ科の花ですが、ヒガンバナとは大きく印象が異なりますね。
毒草で食べると30分以内に嘔吐、下痢、頭痛がおきて、ひどくなると意識消失も起こってきます。
つい先日もスイセンの中毒のニュースがありました。
花が咲いていればわかりやすいのですが、葉っぱだけだとニラに似ているので、間違われて食べてしまうようです。
匂い(スイセンは匂いなし)や、球根の有無(スイセンは球根あり、ニラは球根なし)で見分けられますので、採取するときは根っこから引っこ抜くとわかりやすいと思います。
2022.04.21
春の花-紅梅
桜もあっという間に散り始め、葉桜になりつつあります。
当院の梅も満開になり、下の方は緑色の芽が顔を出してきています。
診察室からもよく見えますが紅梅が満開になりました。
当院には白梅2本と紅梅が1本ありますが、紅梅が一番若いです。
この紅梅は昔からあった梅を接ぎ木したものでした。
しかし、なかなかうまく育たず、苦労したようです。
何回目かの試行錯誤の後、やっとうまくいって成長し花を咲かせるようになってくれたのですが、その途端に元の梅は枯れてしまったとのことです。
不思議なこともあるのですね。
神秘的なものを感じてしまいます。
2022.04.20
春の花-アセビ
日々暖かくなっていきますね。
今回は「アセビ」です。
アセビはツツジ科の植物です。
小さな白い袋状の花がたくさん集まってます。最初ドウタンに似ていると思いましたが同じツツジ科の仲間だったとのことで納得です。
ドウタンよりも茎が短く、花が密集して賑やかな感じですね。
別名を「馬酔木」ともいい、馬が葉を食べると毒にあたって酔っているようにふらふらするということが由来になっているようです。
実際に葉などには「アセボトキシン」という毒が含まれており、当然人間にも有害で、下痢、腹痛、呼吸麻痺などを引き起こします。
逆にこれを利用して殺虫剤にしていたようで、昔の人の知恵ですね。
人だけでなく、昆虫にもこの毒を利用するものがいます。
ヒョウモンエダシャクと言う蛾の仲間で幼虫の時期にアセビの葉を食べて体内に毒を蓄積させるようです。
アセビは英語名で「Japanese andromeda」ともいわれます。
ギリシャ神話のアンドロメダにならってか花言葉は「犠牲」、「献身」となっています。
ところで、この名前はandromeda(ヒメシャクナゲ)に似ていることが由来のようです。
ではこのヒメシャクナゲの花言葉はというと、「警戒」「危険」です。
なぜ、こうなったのでしょうね。
2022.04.13
春の花-椿
温かい日が続きます。先日の梅もあっという間に散り始めています。
今回は「山椿」です。
この写真では紅い椿ですが紅白の色のものもあります。
日本原産の植物で、日本全国で見られます。
2-4月に開花して冬のイメージもありますが春の季語になっています。
花もきれいですが、種からは油をとったりと生活にも必要な植物です。
しかし、花びらが散るのではなく、首元から花が落ちるため死を連想させるとして縁起が悪いとされることもあります。
このためかどうかは不明ですが古い椿には霊が宿るとされています。
江戸時代の鳥山石燕の今昔画図続百鬼にも古椿の霊としてあげられるくらいメジャーな霊だったようです。
石燕の絵では庭先に大きな花をつけた椿が書いてあります。
あちこちに椿に関する怪談があるようですが、実は山形にも椿の怪談があるようです。
旅人を蜂に変えてしまい、自らの花におびき寄せて食べてしまうという恐ろしい話です。
黒緑の葉に囲まれた中に紅い花がぽつんと咲いているのを見ると妖しげな雰囲気がして、昔の人が化けると考えたのも納得できる気がします。
山形の化け椿もまだどこかで咲いているのでしょうか。
そして当院の椿もいつか化けるのでしょうか。想像が膨らみます。
2022.04.09
春の花-梅
四月に入り、日差しも大分暖かくなってきました。
モデルナ社のワクチンも今のところ大きな問題なく接種が進んでいます。
難点はバイアルのゴムが非常に堅く針が刺しにくいところですね。
さて、暖かくなってきたためいろいろな花や芽が次々と出てきています。
まずは梅の花が咲きました。
きれいな桃色の花です。これが咲くと春が来た気分が一気に高まります。
さてこの梅、家に来てから4年ほどたちますが、実をつけるには至っていません。
どのくらいしたら実がなるのかと思って調べてみました。
ことわざでは「桃栗三年柿八年、梅は酸いとて13年」とあるようで、13年、とまでは言わなくてもそれなりに年数は必要なようです。
また、種からの発芽、挿し木、接ぎ木などの条件にもよって変わるようです。
ある程度育ってからいただいたものなので果たして何歳くらいなのかな・・・
さらに調べると花を観賞する「花梅」と果実を収集する「実梅」にわかれるとのこと。
この梅は「花梅」としてもらったので実はつきにくいのですね。
とはいえいずれはなるのでしょうからその日を気長に待ちたいと思います。